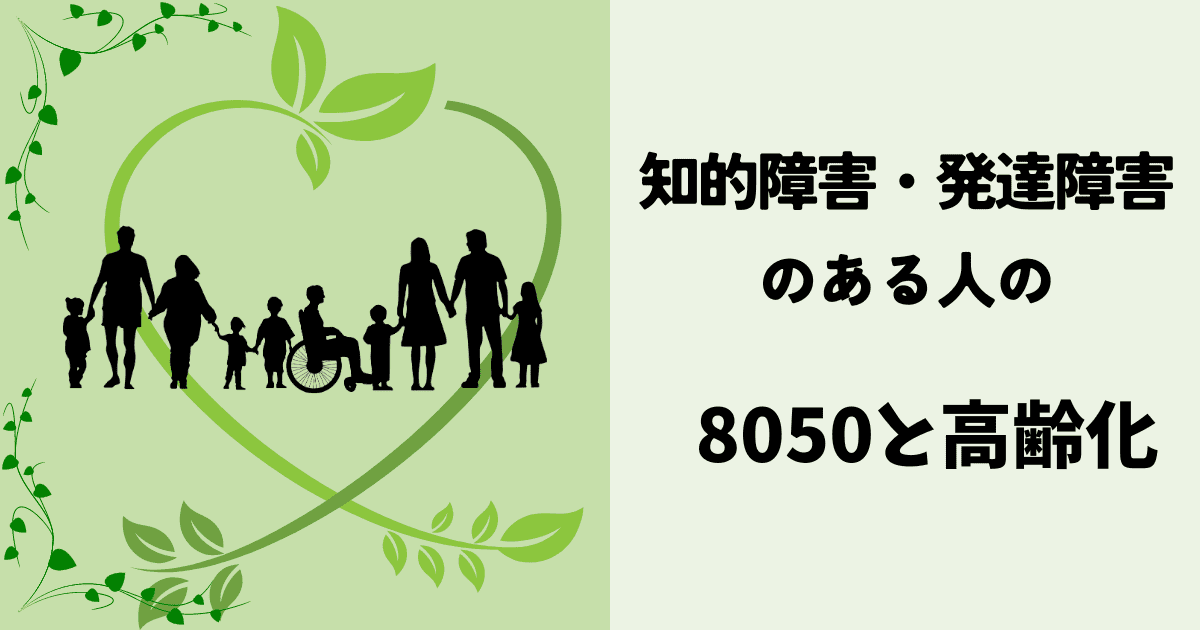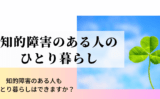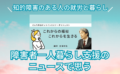知的障害、発達障害のある人の8050問題、高齢化について、又村あおいさん(全国手をつなぐ育成会連合会常務理事兼事務局長)の動画セミナーから分かっていることをまとめました。
今、確認されている出来ることから始めてみましょう。
■参考:2020年6月、2021年5月前半、後半動画セミナー
知的障害、発達障害の8050問題の現状を知る
「8050問題の状況と見通し」について簡単にまとめました。リンクで飛べるようになってますので気になる項目からお読みください。
- どちらが先に亡くなっても生活破綻してしまう3つの相互依存とは?
- 親が80代、子が50代の時に起こる経済的、介助的、心理的な相互依存のことで、主に母子世帯に起こっている問題
- 障害の程度(軽度・中度・重度)による8050問題とは?
- 障老介護(中軽度)
- 老障害介護(重中度)
- 8050問題への手がかり
- 親が60代までに子の人生の見通しを立てる
- 支援に繋がりのある知的、発達障害の場合はリスク回避しやすい
- 支援機関につながっていない場合は、一般的なひきこもり対策支援へもつなげる
- その場合、当事者年齢と相談機関が連携されているかの確認⇒自治体により連携強化がカギとなるため
- 社会全体の悩ましい20年先の未来予測
- 本人が私的なつながりを有する(私的なつながりを支える公的機関はない)
- コミュニティーフレンドについて
- 本人が私的なつながりを有する(私的なつながりを支える公的機関はない)
どちらが先に亡くなっても生活破綻してしまう3つの相互依存とは?
知的障害、発達障害のある人の場合は、どちらが先にいなくなっても生活が破綻してしまう3つの相互依存が指摘されています。それは、母親が80代、子が50代になった今、顕著になっています。
※厚生労働省の「簡易生命表(令和3年)」によると、2021年の日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳。(2022/10月更新)父親よりも母親が長く生きる可能性が高いため、8050問題を母と子に絞っています。
- 経済的相互依存
- 介助的相互依存
- 心理的相互依存
■経済的相互依存⇒親(母親)の年金と本人の年金・給与工賃を合算してなんとか生活を維持しており、どちらが先にいなくなっても生活は破綻する
■介助的相互依存⇒親は自分が若い時の感覚で本人を介助(声かけ・誘導)し、本人は高齢化により心身機能の低下した親に対して物心両面で介助している
■心理的相互依存⇒親は自分が若い時の感覚で「自分がいなければ」と思い、本人は親の高齢化した親の実態を見て「自分がいなければ」と思う
知的・発達障がいのある人へひきつけて考える8050 / スーパー又村塾ONLINE 2020/6/13
障害の程度による「8050」とは?
障害の程度による8050問題では、障老介護や老障害介護といった状況が報告されており、程度による課題は異なるものの深刻になっています。ぜひ、確認ください。
■障老介護⇒軽度障害
支援のアウトリーチや個別対応不足を背景に、50歳代の知的、発達障害者が要介護(支援)状態(特に認知症)にある80歳代の親を介護しているケースが報告されています。
■老障害介護⇒重度障害
社会資源(入所施設やグループホームなどの生活支援系サービス)の不足を背景に、80代の親が通所サービスのみ利用している50代の知的障害、発達障害者と同居しているケースが報告されています。
■中度障害
個々の状況により、障老介護や老障介護にも。
8050問題は、それまでの状況の結果にすぎず要因は5020の時点で既にあると又村さんはいいます。この表から見えてくるのは、その年代の対応の重要性です。
8050問題への手がかり
昨今、長生きしているお年寄り(2022年度)が増えたことで、9060問題という課題も確認されてきました。
又村さんは、親が60代、子が30代の6030時点までに、子の人生の見通しを立てることが7040、8050への歯止めをかけるポイントだ、と言っています。社会との接点や第三者との信頼関係が出来ていない場合は、社会との接点を作りから見直す必要がありますので、親は覚悟を持って対応に当たり、早急に、周囲や行政機関を頼ってほしいと思います。
知的障害、発達障害のある人の高齢化
現行の制度では65歳時に、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行することになっています。しかし、制度上、障害福祉サービスの就労系(就労AB型)は、65歳を過ぎても働けます(但し、注意が必要)
「共生型類型」活用による8050対策
平成30年4月からスタートした「共生型類型」を活用することで、8050世帯の親子利用が可能になりました(後半動画/2021年5月)
共生型とは?
- 法律上は、(前提として)現行の介護保険優先原則を維持(障害者総合支援法第7条規定)
- 平成30年の法改正により、一部サービスで障害福祉サービス事業所が、介護保険サービス事業所を併設できる仕組みを導入(「共生型類型」新設)
- 基幹支援相談センター(障害福祉)と地域包括支援センター(介護福祉)の連携推進も規程

共生型とは、障害福祉事業所が、介護保険サービスの一部を併設している仕組みのこと。一部サービスに限り利用できるよ。
共生型類型で利用できるサービスと事例
- 障害福祉と介護福祉が重なっているサービス
- 介護保険サービスの訪問介護は、障害福祉サービスでは 居宅介護(ヘルパー)
- 介護保険サービスのデイサービスは、障害福祉サービスでは生活介護
- 介護保険サービスの短期入所(ショートステイ)は、障害福祉サービスでも同じ
例えば、親が利用する介護保険サービス事業所が「共生型」で、障害福祉サービスの生活介護を併設した事業所であれば、親子利用が可能(事例あり)
親が利用する介護保険サービス事業所で、子は障害福祉サービス事業の生活介護を利用
例えば、障害福祉サービスの生活介護を利用している方が(65歳で)介護保険サービスに移行する場合、事業所が共生型であれば、これまでと同じ事業所に通所できます。(環境を変えずに通所できる。
生活介護(障)を利用していた方がデイサービス(介)として、同一事業所で利用できる→これまでは、別の事業所を探さなくてはいけなかった。

障害福祉事業所が、介護保険サービス事業所の①訪問介護②デイサービス③ショートステイを併設していれば、利用できるんだ。
介護保険サービスと障害福祉サービスは別のサービス
介護保険サービスと障害福祉サービスは別事業です。障害者総合支援法第7条には、65歳(及び65歳前でも)条件を満たして介護保険制度を利用できる場合は、介護保険制度が優先されるとあります。
介護保険サービスと障害福祉サービスは別事業
共生型で心配されている課題
これまで障害のある人の福祉サービスは、65歳になると介護保険サービスに移行しました。しかし、「障害福祉サービスを利用したい」という声を受け、平成30年に法改正され、新しく共生型類型が導入されました。
しかし、課題も見えていますので注意が必要です。
- (介護保険サービスへ移行する時)利用している事業所が、共生型サービスへの移行しているか?
- 週5日利用可能な要介護認定が出るか?の保証がない(知的障害、発達障害の要介護認定が肌感覚として軽くなりがち→ 分析データはないが…)
- 利用者負担の軽減対象に課題(60歳時点でのサービス利用状況で軽減の可否が決定)
■障害福祉事業所が共生型サービスへ転換している事業がない
共生型は、報酬が低いので事業所にとってメリットがない。そのため、転換できるか?
■知的障害、発達障害の要介護認定が(又村さんの肌感覚として)軽くなりがち
障害区分4が、介護の要介護2、1になる可能性が!そうなると、障害福祉では5日通えてたサービスが、介護サービスだと3日しかないなど困った事態を想定できます。なので65歳前に役所窓口に5日を
■利用者負担の軽減対象が課題
介護保険サービスは、原則1割負担。しかし、障害福祉から介護福祉に移行する際は、特例があります。(条件を満たせば負担ゼロ)ただ、条件が厳しいことも頭に入れておいてください。
- 利用負担軽減対象者は、65歳以前の5年間にわたり、居宅介護(ヘルパー)か、生活介護、ショートステイの受給決定を受けている支援区分「2」以上で低所得者(利用負担ゼロ)の者
- 65歳になるまで介護保険サービスを利用していない
- 軽減対象になれば、他所事業所を利用する場合も負担軽減

60歳の時点でヘルパー、生活介護、ショートステイを利用していれば、利用負担軽減可。就労ABは、65歳を過ぎても利用できるけど、介護保険サービスへ移行した場合は1割負担になるんだって。難しいねー。
障害基礎年金受給者について
障害基礎年金を受給されていることが前提で、3つのポイントをあげていました。
- .障害基礎年金を受給している場合、65歳到達しても老齢基礎年金への切替は不要(老齢基礎年金と障害基礎年金2級が同額)
- ただし、企業就労していた場合には「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組合せで受給可能
- 障害基礎年金だけでは生活費が不足するため、何らかの私的な備えが必要
障害基礎年金だけでは、生活費が不足することを知って、早目に対策下さい。
- 障害基礎年金1級の方は老齢基礎年金に切替えると減額されるので注意(65歳切替え不要)
- 就労していた人(企業就労・就労A型で社保加入)は、障害基礎年金に「老齢厚生年金」が上乗せされるので申請が必要→65歳になったとき、手続きを行える人を確保
- 何らかの私的な備えが必要(扶養共済年金、特定贈与信託など)
障害基礎年金を受給していない方やひきこもっている方の場合は、こちらの記事がわかりやすかったのでお読み下さい。
知的障害、発達障害のある人の住まいについて
高齢になった知的障害、発達障害のある人の住まいについては、3つのケースが考えられています。
在宅(親御さんの持ち家)か?グループホームか?入所施設か?
- 在宅の場合は居宅介護(重度訪問介護)を活用して親なきあとも独立生活ケースあり
- グループホームは「日中サービス支援型」が制度化され、重度高齢化にも対応(ただし、認知症の診断が出た場合は原則として介護保険へ移行)
- 入所施設は介護保険の適用除外(65歳以上退所者の半数は看取り対応)
親御さんが持ち家の場合、福祉制度を利用しながら在宅で暮らすケースは今や珍しいことじゃないようです。また、入所施設の場合は、介護保険適用除外なので、入所施設は亡くなる(看取り対応)までそのまま入所施設にいられるようです(退所の場合は、亡くなるか、入院か、特別養護老人施設か)
住まいに関しても、それぞれに早目の対策が必要ですね。
- グループホームの場合は、65歳時に認知症の診断が出るか?出ないか?で対応が変わる→ 診断が出ると原則、介護保険制度へ移行するようなので注意が必要
社会全体の20年先の未来予測~又村さんセミナーから~
超少子高齢化社会の真っただ中にいる私たちは、制度改革が進む一方で自己解決を身に付ける時代に突入したのかもしれません。しかし、課題に解決策が無いわけではありません。又村さんからヒントも頂きましたので、お伝えしたいと思います。
■8050問題を前向きに解決するためには
知的・発達障がいのある人へひきつけて考える8050 / スーパー又村塾ONLINE 2020/6/13
- 本人が何らかの人的つながりを有すること
- 友人や趣味活動、行きつけの店でも良いので(社会との接点)つながる
- 公的な各種相談窓口、福祉サービスなどとつながる
本人が、なんらかの人的つながりを有することが、8050問題に立ち向かうこと。私的なつながりを支えるための公的機関はない。
スーパー又村塾ONLINEセミナー2020/6月より
とはいえ、コミュニケーションのとれない我が子が、どうやって私的なつながりを確保できるのか?という不安もありますが…。
コミュニティーフレンド
先駆的な取り組みを開始しているNPO法人をご紹介します。
障害のある子の親たちで設立したNPO法人PACガーディアンズさんの取り組みが、私的なつながりを後押しする事業として、全国的に有名です。(又村さん情報)事業名はコミュニティーフレンド。

コミュニティーフレンドとは、ヘルパー支援でも日中一時支援でもなく、ちょっとしたサポートがコンセプトの事業です。
コミュニティー内の友達という位置づけで、「一緒に同じ趣味を楽しむ」というスタンスだそうです。
法人は、(障害のある人と同じ趣味を楽しめる)友人を募集し、関わり方をレクチャー、サポートしています。
親同士のつながりで、障害のある子を支える取り組みが今後、更に注目されそうですね。
参考動画
もっと詳しい内容を知りたい皆さんは、又村さんのセミナーを必ず視聴ください。
【2020年6月㈱ドコモ・プラスハーティ】
【2021年5月ぜんち共済㈱】
制度は、どんどん変わってゆきますのでその都度、最新の情報をアップデート下さい。