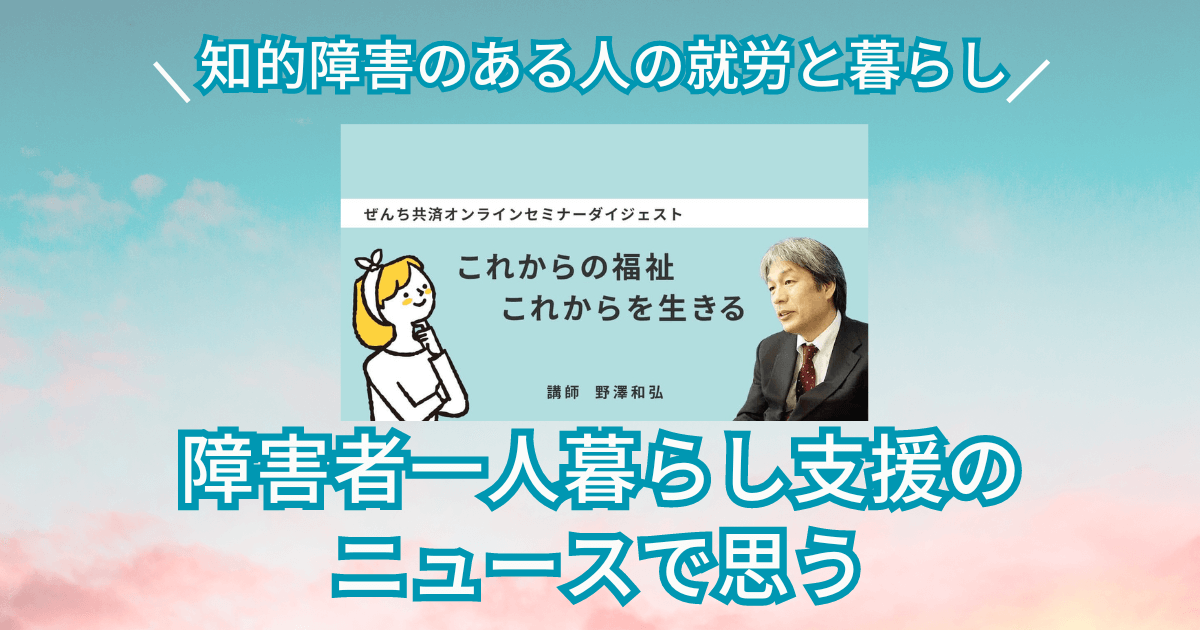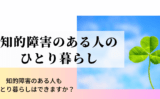毎日新聞の見出し「厚労省、障害者の一人暮らし支援に特化したグループホーム創設へ」を読んで、すぐに野澤和弘さんのオンラインセミナーを思い出しました。
野澤さんのセミナーでは、障害者総合支援法改正案の中間とりまとめについて解説し、
今回のニュースについても語っていました。
この記事は、国が創設するグループホーム(以下GH)について、2022年4月に開催された野澤さんのセミナーとリンクしながら当事者家族として思ったことを綴ります。
住居は訓練の場ではない
一人暮らし支援に特化したGHが、原案に上がってくるのは嬉しいことです。「一人暮らしできるかも!」と親としての期待値はあがります。
でも、国が打ち出しているのは、東京都が精神障害のある方を対象とした試行的にやっている通過型グループホーム(2年限定)のようです。
その内容に、現場からは「住居は訓練の場ではない」の声が上がっています。それは、私の心にも強く残りました。
確かに、住居を訓練の場にすることは、当事者にとっては辛い。自身に置き換えてみると皆さんも想像できるのではないでしょうか。
今の現状で…となると、一人暮らしを試したけど上手く移行できない障害のある人の姿が、なんとなく見えてきます。
住まいの場を障害者の訓練という捉え方で支援しようとしている現状に、皆さんはどう答えをだしてゆくでしょうか。
これからの福祉・これからを生きる(ぜんち共済オンラインセミナー 2022.4.23)
- 障害者のライフステージを見据えた支援や障害者の地域生活支援施策の全体像が見えないための不安
- 一人暮らし等に向けた支援はピアサポーターのは一が有効
- 地方ではまとまったニーズがなく整備が進まないのではないか
- 一人暮らし等への移行により空室が生じるため安定的な事業運営が難しい
- 報酬上の実績評価については、障害の状態像等を踏まえた一人暮らし等に向けた支援の困難度を勘案して評価すべき
施策提案の背景にあるもの
今、なぜこのグループホーム(GH)が議論に上がっているのか?といえば、当初は約10万人を想定していた利用者数が、現在14万人になったことで国が予算の見直しと問題提起を行っているといいます。
また、一人暮らしを後押しした制度(自立生活援助)が、地域で上手くいっていないということも要因になっているのです。
国はGHを増やさない方針のようなので、今後どう障害のある人の自立を手助けするのか?という一歩踏み込んだ支援制度が必要になりそうです。

改正にあたって居住支援についての資料が厚労省がUPされています。
こちらもチェックしてくださいね。
通過型GHで一人暮らしは可能になる?
支援サービスの期限終了後に、本当に一人暮らしが可能になるような結果になるのでしょうか?
報告書では「障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、本人が希望する1人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなGHのサービス類型を検討すべきだ」
毎日新聞 2022/6/13 18:37(最終更新 6/13 18:37)
本人が希望する一人暮らしに向けた支援。
報告書の文言は、とてもキラキラしています。でも、本当に現実的な支援策なのでしょうか。
国の税金を投入するのなら、確実にこの事業が目的を果たせるような仕様(ある程度のステップ)にしなければいけないのでは?と思います。
今後も要チェックです!!