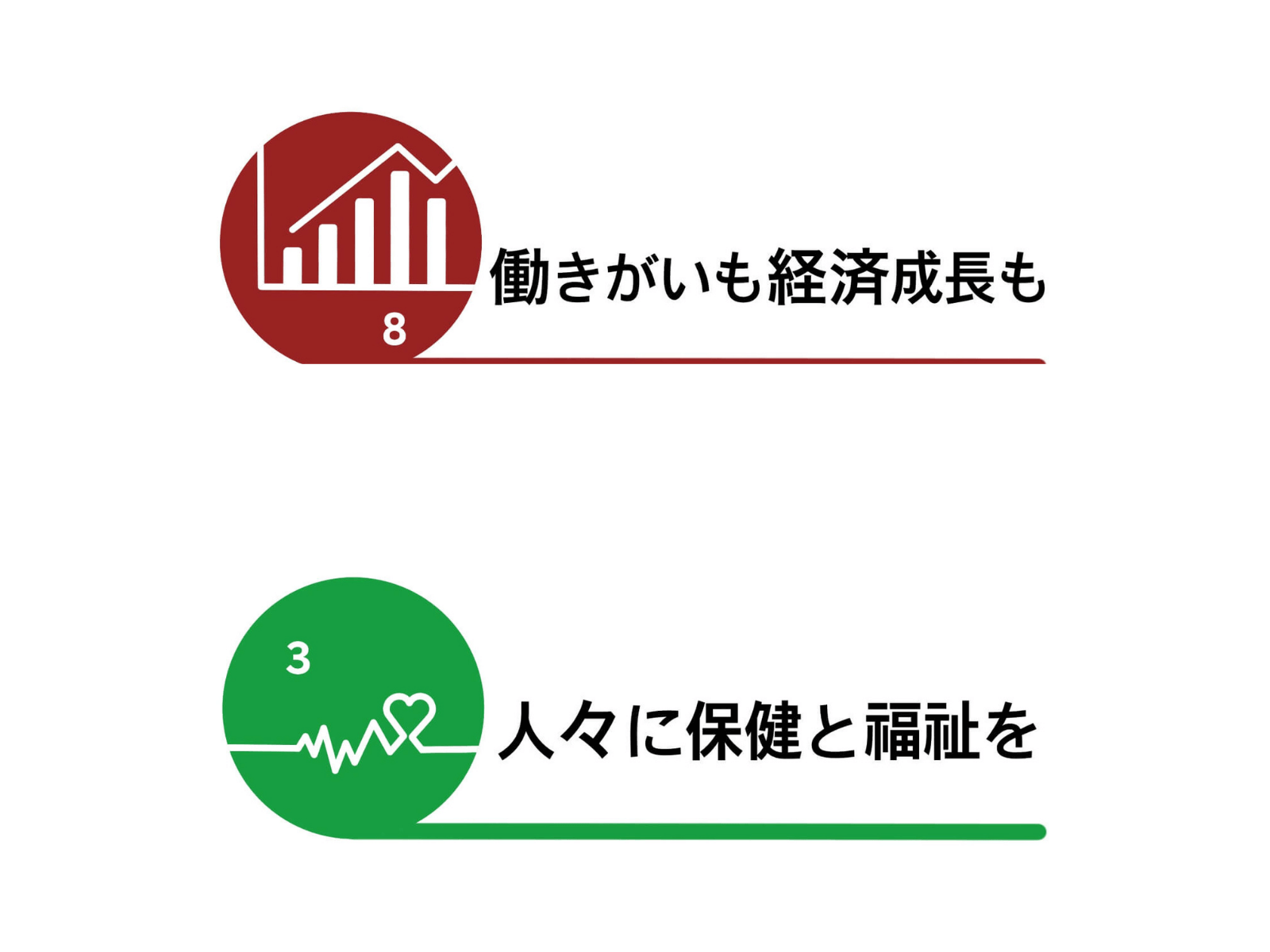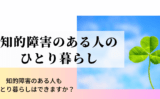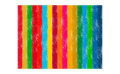特別支援学校高等部や一般高校を経て、企業で働く知的障害のある人は増えています。しかし、就労後にどのように支援されているのか?そもそも障害者雇用と福祉施策の連携は上手くいっているのか?などは不透明でした。
この記事では、2021年6月に公表された膨大な報告書内容から、一部に触れてお伝えしたいと思います。

今回のテーマはココ!!
障害者雇用と福祉の連携について国が縦割りから生じる課題があることを認めているよ。
令和5年、美咲特支から20人「一般就労」で内定のニュースから
2023年3月21日の琉球新報で、美咲特別支援学校から20人「一般就労」内定のニュースが飛び込んできました。
軽度知的障害のある生徒が通う沖縄県内の高等支援学校5校だけでなく、特別支援学校の高等部は、卒後の就労を目指した試みが始まっていたことを知りました。
…ということは、両施策(障害者雇用・福祉の連携)の縦割りから生じる課題や制度の谷間から不十分な状況の解消に向けた取り組みを加速させる必要があると思います。
制度から外れた就労している知的障がいのあるひとたち
卒業後、直ぐに就労した知的障害のある人たちの課題については、親の会の活動で開催した覆面ユンタク会(限定人数での非公開)でも、度々聞かれてきました。
ただ、裏付けとなるような実態調査がないため、その人だけの課題なのか?それとも一定数、このような状況下にいる人たちがいるのか?など、(親の会が認識してから)10年近くも不透明なまま過ぎました。
2021年6月、障害者雇用と福祉連携の卒後課題についてやっと 障害者雇用・福祉施策との連携強化に関する検討会報告書が厚生労働省から公表されました。
検討会報告書の「はじめに」には、 両施策の制度が縦割りになっていることから生じる課題や「制度の谷間」から十分に対応できていない状況等が顕在化(厚生労働省引用)と書かれています。

これでやっと就労と福祉の連携が不十分だったことが明確化されたんだ。
国と課題が共有ができたことは大きいね。

NPO法人Alon Alon理事長 那部智史氏 のFB記事でも取り上げていたよ~。
障害者就業・生活支援センター(通称・ナカポツセンター)
沖縄県では、知的障害のある生徒が高等学校卒業後、すぐに企業就労した場合の支援先は(離島含めて6つ)障害者就業・生活支援センター(通称:ナカポツ)が担います。
これまで通り、ナカポツセンター(障害者就業・生活支援センター)の取り組みが期待されていますが、検討会報告書では、課題について次のように報告されました。
一方、卒業後すぐに企業等に就職した者に対する定着支援については障害者就業・生活支援センターが中心に実施している地域が多く、その支援対象者が年々増加する中で、質・量ともにどう対応するかが大きな課題となっている。
障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書
注目してほしいのは質・量ともにどう対応するのかが大きな課題となっているところです。
沖縄県では、平成25年(2013年※)から、卒業生保護者の相談を経て沖縄高等特別支援学校卒後課題として相談、陳情し、県議会で議論されてきました。
そして令和2年(2020年)4月には、課題解決策の一つとして、南部地区ナカポツセンターが追加で設置されました。※卒後に関連したこれまでの経緯を沖縄県議会議事録検索できます。
しかし現時点では、両施策の縦割りから生じる課題や制度の谷間から不十分な状況であることに変わりはありません。
特に軽度知的障害のある子の就労を目的とした沖縄県内の特別支援学校 5校(沖縄高等特別支援学校・中部農林・陽明・南風原・やえせ高等支援学)はもちろんのこと、県内の就労を後押ししている特別支援学校のでの課題共有は必須です。そして、解決に向けた具体的な対策が必要です。

先ずは保護者の皆さんと課題が共有されるといいよね。

そうだね。卒業後の課題に対する意識はを保護者のみなさんで共有したいですね~
障害者雇用と福祉連携はスタート地点に立ったばかり!
報告書のポイントが公表されています。課題は山積みですので、ぜひ、確認してください。
また、それぞれの検討会の議事録では、どんな風に議論されていたのか、確認することができますのでぜひ!