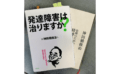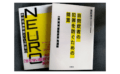2022年から、発達障害は「神経発達症」という名称に変更しました。
この記事は、神経発達症(発達障害)は、神経に着目するといいかも?というテーマで考えてみました。
発達障害は「神経発達症」になった
ものすごくザックリですが、神経発達症の名称変更までの流れです。
- 2013年5月、アメリカ精神医学会の診断基準が「DSM-5」に改訂
- 2019年5月、第11版(ICD-11)が承認
- 2022年1月、日本で神経発達症という名称に変更
始まりは、2013年のアメリカ精神医学会の診断基準が「DSM-5」に改訂されたことですが、「第22回社会保障審議会統計分科会、傷害及び死因分類専門委員会 議事録」を読むと、日本は診断名に右往左往してきたことが分かります。
発達障害=脳機能障害は、心理的な負担が大きい
医師や専門家から、「発達障害=脳機能障害」と伝えられたことで、親は長い間、育てる力を削がれてきました。名称変更の理由は、かなりの衝撃を親御さんに与えてきた、と議事録にはありました。
また小児の方々も、患者さん家族に「あなたのお子さんはなんとか障害です」という病名を伝えると、かなりのネガティブインパクトを与えるということから、まずDMS-5で、その領域の障害を「症」に変えました。
https://kohaken.net/20200509icd11/
私は、「ネガティブインパクトを想像できなかったのはどうしてなのか?」と、親の立場として単純に思います。発達障害を苦にした無理心中を図ったニュースは多くありましたし、実際のところ子育ての手立てを療育者に伝授できていないのです。
私も「脳機能障害(=発達障害)の我が子をどう育ててゆけばいいのか?」と常に悩みの渦中にいましたから、焦りと苦痛でいっぱいになった子育ての発想は、どんどん削がれていったことを思い出します。
発達障害=脳機能障害では、心理的な負担が大きいのです。
「神経発達症」なら神経に着目するといいのかも?
花風社から出版されている「発達障害は治りますか?/2010年」の中で、精神科医神田橋先生は、神経発達症(発達障害)を「脳のシナプスの発育の遅れ」といっています。
臨床医の知見は、神経発達症(発達障害)のある人の可能性を信じさせ、生活に支障のあった患者の状態を治しています。
本を読むと見えてくるのは、神経発達症(発達障害)の実情です。
特に思春期、青年期以降の課題を押さえて子育てをするといいのかな、と思います。
また、神経発達症になってからの精神医療は、漢方処方も正式に入ってきたようです。向精神薬一択だった時代から考えると大きなポイントになりますね。
変更のポイントには、伝統医学(主に中国・日本・韓国の漢方)の内容も入りました。
以前から発達障害症状に漢方が効果的と主張する医師の方も存在していましたので、今後は目にすることも増えるかもしれません。(漢方は副作用も少ないらしいので、安心感はありそうです。)
こども発達支援研究会



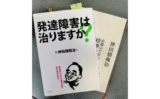
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20016012.464684dd.20016014.8f1d53d4/?me_id=1213310&item_id=18284861&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5983%2F9784907725983.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)